日本最大の預金機関がステーブルコインに類似した通貨を発行へ
日本最大の預金機関であるJapan Post Bankは、2026年度に「DCJPY」と呼ばれるトークン化預金通貨を導入すると発表しました。
最近、日本最大の預金機関であるJapan Post Bank(日本郵政銀行)は、2026年度に「DCJPY」と呼ばれるトークン化預金通貨を導入することを発表しました。この取り組みは、ブロックチェーン技術を活用して証券決済プロセスを最適化し、日本経済におけるより広範な応用を模索することを目的としています。Nikkeiの最新報道によると、この計画は日本の金融機関が分散型台帳技術を深く受け入れることを示しており、金融インフラの効率を大幅に向上させるとされています。
DCJPYの誕生と技術基盤
DCJPYは、日本のInternet Initiative Japan(IIJ)グループ傘下の子会社DeCurret DCPによって開発されたデジタル通貨システムです。このシステムは2024年8月に正式に設立され、同年9月にはDeCurretがDCJPYのビジネスインフラ強化のために約63.5億円の資金調達に成功しました。Japan Post Bankのパートナーとして、DeCurret DCPは三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG、日本最大の金融機関)など複数の金融機関から支援を受け、60社以上の企業によるアライアンスを形成しています。これにより、DCJPYは強固な資金と技術のバックアップを得るとともに、規制枠組みの下でのコンプライアンスも確保されています。
DCJPYの為替レートは日本円と厳格に連動しており、1:1の比率(1DCJPY=1円)を採用しています。ユーザーは専用口座を既存の預金口座と連携させることで、残高の即時交換や償還が可能です。この設計は銀行預金のデジタル化形態に類似していますが、許可型ブロックチェーンネットワーク上で運用されます。従来のステーブルコインとは異なり、DCJPYはパブリックブロックチェーン上で発行されるのではなく、ライセンスを持つ金融機関が管理するプライベートネットワーク内に限定されています。これにより、日本金融庁(FSA)の規制要件により適合し、グローバルなステーブルコインがもたらす可能性のある越境リスクやボラティリティの問題を回避しています。
Japan Post Bankは日本最大のリテール預金規模を誇り、約1.2億の口座と総預金額1.29兆ドル(約190兆円)を有しています。この膨大なユーザーベースは、DCJPYの発行に大きな可能性をもたらします。銀行は、休眠口座などの遊休資金をDCJPYトークンに転換し、証券型トークン(Security Tokens)の購入に利用できるようにする計画で、目標利回りは3%から5%としています。これにより、若年層の投資家を惹きつけ、従来の貯蓄からデジタル資産への転換を促進します。
ユースケースと効率向上
DCJPYの主な用途はデジタル証券決済に集中しています。現在、日本の証券取引の決済サイクルは通常T+2(取引実行後2営業日)ですが、DCJPYを利用することで、ユーザーはほぼ即時の取引決済が可能となり、時間を大幅に短縮し運用コストも削減できます。アナリストによれば、この変革により銀行は年間数十億円のコスト削減が見込まれます。さらに、Japan Post BankはDCJPYを地方自治体の補助金支払い分野にも拡大することを検討しており、地方自治体と連携して補助金や助成金のデジタル配布を実現し、公共プロセスの簡素化や透明性・効率の向上を目指しています。
最近のテストプロジェクトでは、DCJPYの潜在能力が示されています。DeCurret DCPのパイロットには、証券決済のシミュレーション、銀行間送金、政府補助金の配布が含まれ、総取引額は20億円を超えています。現在、GMOあおぞらネット銀行が唯一公表されているDCJPY発行銀行ですが、Japan Post Bankの参入によりネットワーク規模はさらに拡大します。Boston Consulting Group(BCG)とRippleのレポートによれば、世界のリアルワールドアセット(RWA)トークン化市場は2025年の6000億ドルから2033年には18.9兆ドルに成長すると予測されており、Japan Post Bankの取り組みはこのグローバルトレンドに合致しています。
ステーブルコインとの違いと規制環境
DCJPYは外部から「ステーブルコインに類似」と呼ばれることもありますが、規制上の定義では「トークン化預金(Tokenized Deposits)」により近い存在です。今年初めに日本初のステーブルコインライセンスを取得したJPYCとは異なり、JPYCのようなステーブルコインは通常パブリックブロックチェーン上で発行され、グローバルに流通し、第三者担保によって裏付けられています。一方、DCJPYは許可型ブロックチェーンに限定され、銀行が直接裏付け、実際の預金残高を表します。これによりセキュリティが向上し、日本の厳格なマネーロンダリング対策(AML)や顧客確認(KYC)要件にも適合します。
2025年、日本のステーブルコイン規制は大きく加速しています。日本金融庁は秋に初の円連動型国産ステーブルコインの発行を承認する予定であり、これが金融機関のイノベーション意欲をさらに刺激しています。Japan Post BankのDCJPY計画はこのような背景で打ち出されており、規制当局のブロックチェーンに対する積極的な姿勢を反映しています。同時に、日本政府は暗号資産取引の20%キャピタルゲイン税の引き下げや、デジタル資産ETFの導入に向けた税制改正も検討中です。これらの政策はDCJPYなどのプロジェクトにより良い環境を提供するでしょう。
競争激化と相互運用性の課題
Japan Post Bankの参入により、日本のフィンテック業界の競争はますます激化しています。他の大手銀行では、SBIグループがChainlinkと提携し、クロスボーダー決済やサステナビリティプロジェクトを模索しており、三菱UFJやみずほフィナンシャルグループもデジタル通貨アライアンスに積極的に参加しています。この競争は銀行間にとどまらず、FinTech企業やソフトバンク傘下のPayPay決済システムなどのテック大手にも広がっています。Japan Post Bankの高齢ユーザー基盤(多くの口座が高齢者所有)と若年投資家のニーズの融合は、デジタル化転換において優位性をもたらすでしょう。
しかし、相互運用性は依然として重要な課題です。規制やセキュリティの観点から、証券型トークンは現在主に許可型ブロックチェーンで発行されており、クロスプラットフォームの互換性問題が顕著です。DeCurret DCPのネットワークはモジュラー設計(金融エリアと商業エリアを含む)ですが、パブリックブロックチェーンや他のプライベートネットワークとのシームレスな接続を実現するにはさらなる技術革新が必要です。専門家は、この課題が解決されれば、DCJPYは日本国内にとどまらず国際決済にも拡大し、日本のグローバルデジタル金融における影響力を高める可能性があると指摘しています。
今後の展望:日本デジタル経済の転換点
Japan Post BankのDCJPY計画は、単なる技術アップグレードにとどまらず、日本経済のデジタル化戦略における重要な一歩です。膨大な遊休資金を活性化し、デジタル資産エコシステムに注入するとともに、CBDC(中央銀行デジタル通貨)の将来への道筋も築きます。グローバルな視点でも、この取り組みはイノベーションと規制のバランスにおける日本のリーダーシップを示しています。2026年が近づく中、市場はDCJPYがより効率的で包摂的な金融サービスをもたらし、日本が伝統的金融からWeb3時代への円滑な移行を果たすことを期待しています。
さらにWeb3ニュースを見るには......Techub News APPをダウンロード

QRコードをスキャンしてTechub APPをダウンロードし、さらにWebニュースをチェック
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか?
韓国、ステーブルコイン規制の迅速な対応を要求
韓国の与党は、政府に対してステーブルコイン市場を迅速に規制するよう圧力をかけています。ステーブルコイン発行のために銀行が関与するコンソーシアムモデルが検討されています。この規制は、通貨主権を強化し、米国のステーブルコイン支配とのバランスをとることを目的としています。

Pi Networkが暗号資産の最大の課題にどのように正面から取り組んでいるかを発見
要約 Pi Networkは2025年が近づく中、依然として$0.30未満で取引されています。今後3〜5年は、Pi Networkおよび暗号資産のより広範な普及にとって重要な期間です。イノベーションと正しい枠組みが、暗号通貨の将来にとって極めて重要です。
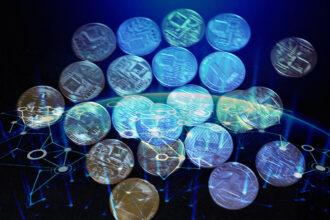
Ripple XRP価格予測 2025-2030:XRPは5ドルに到達できるか?
Cardano ADAの価値が証明された:アルトコイン崩壊をどう乗り越えたか
